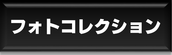2013年07月08日
MRI
「ヘルニアではなさそう、でも念のため」ということで、首のMRIを受けることに。
「機械の音がしている間は動かないように。画像がボケてしまいます。
つばをゴクッっていうのもダメですよ」って。
約20分間。
真上を向いたまま寝そべって、まったく動けない。
ふと眠気が襲ってくる。
すると喉の奥の緊張がなくなり、急に喉チンコが中に落ち込むのだろう。
イビキの一歩手前。息ができなくなって、グェッて。
あっ、ビックリ。一気に正気にもどる。
(実を言うと、小生ときどき、睡眠時無呼吸症候群ってヤツになるらしい)
でもまたしばらくすると眠くなり、グェってなる。
そんなことを数回繰り返し、画像にボケがないか心配なまま撮影は終了したのであった。
続きを読む
「機械の音がしている間は動かないように。画像がボケてしまいます。
つばをゴクッっていうのもダメですよ」って。
約20分間。
真上を向いたまま寝そべって、まったく動けない。
ふと眠気が襲ってくる。
すると喉の奥の緊張がなくなり、急に喉チンコが中に落ち込むのだろう。
イビキの一歩手前。息ができなくなって、グェッて。
あっ、ビックリ。一気に正気にもどる。
(実を言うと、小生ときどき、睡眠時無呼吸症候群ってヤツになるらしい)
でもまたしばらくすると眠くなり、グェってなる。
そんなことを数回繰り返し、画像にボケがないか心配なまま撮影は終了したのであった。
続きを読む
Posted by てつじ です at
20:28
│運動・スポーツ・健康
2013年07月07日
しゃべる自販機
昨日のブログでしゃべる自販機の話をしたら、結構ウケてたみたいなので、もう一つ。
もう25年くらい前に聞いた話。しゃべる自販機が出始めもの頃。
ある人がタバコを自販機で買ったら、「ありがとうございました。もう一箱いかがですか?」って自販機がしゃべった。
これは面白いと、もう一箱買ったら、「ありがとうござました。もう一箱いかがですか?」って。
ずっとこの調子かな?と思い、何箱か続けて買ってみた。
そしたら「ありがとうございました。健康のために、吸いすぎに注意しましょう」って、おせっかい。
こんなに買ってしまったのは、お前のせいだってぇの。
続きを読む
もう25年くらい前に聞いた話。しゃべる自販機が出始めもの頃。
ある人がタバコを自販機で買ったら、「ありがとうございました。もう一箱いかがですか?」って自販機がしゃべった。
これは面白いと、もう一箱買ったら、「ありがとうござました。もう一箱いかがですか?」って。
ずっとこの調子かな?と思い、何箱か続けて買ってみた。
そしたら「ありがとうございました。健康のために、吸いすぎに注意しましょう」って、おせっかい。
こんなに買ってしまったのは、お前のせいだってぇの。
続きを読む
2013年07月06日
2013年07月05日
Bahasa Indonesia tidak mudah belajar !
Saya mencoba menerjemahkan artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia.
Sangat susah !
Makin panjang teks, makin susah.
Banyak orang kata bahwa bahasa Indonesia mudah belajar.
Tetapi itu salah.
Saya merasa tatabahasa bahasa Indonesia aneh sekali.
Lebih baik saya belajar dengan sungguh-sungguh lagi.
インドネシア語で書かれた資料を翻訳してみた。
すごく難しい!
文章が長ければ長いほど難しい。
多くの人がインドネシア語は簡単だと言う。
しかしそれは違う。
私は、インドネシア語の文法ってとても変わっていると思う。
私はもっと一生懸命勉強した方が良いのです。
Sangat susah !
Makin panjang teks, makin susah.
Banyak orang kata bahwa bahasa Indonesia mudah belajar.
Tetapi itu salah.
Saya merasa tatabahasa bahasa Indonesia aneh sekali.
Lebih baik saya belajar dengan sungguh-sungguh lagi.
インドネシア語で書かれた資料を翻訳してみた。
すごく難しい!
文章が長ければ長いほど難しい。
多くの人がインドネシア語は簡単だと言う。
しかしそれは違う。
私は、インドネシア語の文法ってとても変わっていると思う。
私はもっと一生懸命勉強した方が良いのです。
2013年07月04日
イギリスの霧
「霧のロンドン」なんて言うが、イギリスは、ロンドンでなくても何処へ行っても霧が多い。
一度凄い霧に遭遇したことがある。ロンドンの北西150kmくらいの位置だったと思う。
イギリス(イングランド地方)には山がほとんどなく丘ばかり。
だから、日本の霧のように標高が高くなるにつれてだんだん濃くなっていくというイメージではない。
ある夜、車で走っていた。小さな丘を登ったり下ったり。
そしたら、道の向こうに何か白い物が。
だんだん近づいていったら、なんと物凄い濃い霧。
まさに『霧の塊』。その周りは何でもないのに、そこだけ真っ白い霧。
まるで物凄く大きな綿菓子をポンっと置いた感じ。
その霧の中へ突っ込んで行ったら、フロントガラスの上を『霧の塊』が流れていく。
そして百メートルほど走ったら、霧から抜け出た。
出たら、その先には全く霧はない。
後ろを振り向いたら、やはりそこには『霧の塊』。『霧の塊』がだんだん遠のいて行く。
イギリスでは何度も霧に遭遇したが、こんなに不思議な霧はこれ1回きりだ。
 続きを読む
続きを読む
一度凄い霧に遭遇したことがある。ロンドンの北西150kmくらいの位置だったと思う。
イギリス(イングランド地方)には山がほとんどなく丘ばかり。
だから、日本の霧のように標高が高くなるにつれてだんだん濃くなっていくというイメージではない。
ある夜、車で走っていた。小さな丘を登ったり下ったり。
そしたら、道の向こうに何か白い物が。
だんだん近づいていったら、なんと物凄い濃い霧。
まさに『霧の塊』。その周りは何でもないのに、そこだけ真っ白い霧。
まるで物凄く大きな綿菓子をポンっと置いた感じ。
その霧の中へ突っ込んで行ったら、フロントガラスの上を『霧の塊』が流れていく。
そして百メートルほど走ったら、霧から抜け出た。
出たら、その先には全く霧はない。
後ろを振り向いたら、やはりそこには『霧の塊』。『霧の塊』がだんだん遠のいて行く。
イギリスでは何度も霧に遭遇したが、こんなに不思議な霧はこれ1回きりだ。

2013年07月03日
2013年07月02日
ビールコースター @ England
20数年前、イギリスロンドンから車で2時間くらいの所にあるDroitwichという片田舎に住んでいた。
スコット、ディーン、タニア達と、よく飲みに行ったものだ。毎週末どこかのパブに行った。
イギリスには地ビールがたくさんあって、各々のパブで出てくるビールが違っていたりする。
カウンターに行って「パイントラガー」って注文する(訛りが強い人は「パイントラギー」と言っていた)。
ちなみに、1パイントは568ml。だから生中よりちょっと大きめ。
1回1回その都度、お金を払う。
そうすると、ビールサーバーからその店が契約している地ビールをグラスに注いでくれる。
ビールグラスと地ビールのコースターを渡される。
店によって扱っているビールが異なるので、あっちこっちのパブに行くと色々なビールコースターが手に入る。
これを集めるとなかなか楽しいし、おしゃれなんだよね。

 中には、裏に1コママンガが書かれていたりするんです。
中には、裏に1コママンガが書かれていたりするんです。
続きを読む
スコット、ディーン、タニア達と、よく飲みに行ったものだ。毎週末どこかのパブに行った。
イギリスには地ビールがたくさんあって、各々のパブで出てくるビールが違っていたりする。
カウンターに行って「パイントラガー」って注文する(訛りが強い人は「パイントラギー」と言っていた)。
ちなみに、1パイントは568ml。だから生中よりちょっと大きめ。
1回1回その都度、お金を払う。
そうすると、ビールサーバーからその店が契約している地ビールをグラスに注いでくれる。
ビールグラスと地ビールのコースターを渡される。
店によって扱っているビールが異なるので、あっちこっちのパブに行くと色々なビールコースターが手に入る。
これを集めるとなかなか楽しいし、おしゃれなんだよね。
続きを読む
2013年07月01日
始まりました「安全月間」
 毎年7月1日から7日までは、中央労働災害防止協会の「全国安全週間」 です。
毎年7月1日から7日までは、中央労働災害防止協会の「全国安全週間」 です。この時期は発汗量が増え感電事故が多くなるためと聞いたことがあります。
タカラ産業では、毎年7月を『安全月間』と位置付け、安全に関する啓蒙活動を行っています。
私の知る限りではタカラ産業(旧中央製機)で感電事故は発生したことがありませんが、いわゆる“赤チン災害”や“労災事故”というものはあり得ます。
やはり、事故やケガはない方が良いのです。
今日の朝礼でこんな話をしました。
「KYT(危険予知トレーニング)」という言葉があります。
これは、その作業に潜む危険を事前に予知し、そうならないように注意して作業を行えば事故は起こらないという訓練です。
逆に言えば、危険に頓着なく、無意識、無防備で仕事をすると、非常に危険だということです。
「このくらいいいだろう」や「自分は大丈夫だ」といった慣れや甘えは禁物です。
みんなで声を掛け合って、自分達の力で安全職場を築き上げましょう。
続きを読む